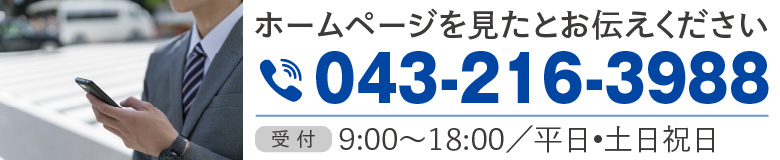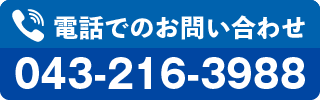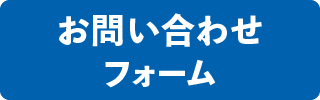このページの目次
退職時のトラブルは増加傾向
退職時のトラブルが増加傾向にある現代において、労働者と会社の関係が円滑であれば、就業規則上の問題は滅多に生じません。しかしながら、キャリアアップなどといった理由を表向きに挙げていても、実際には円満退職とは言い難いケースが多いのが現実です。実際には退職という行為は、関係が良好であるからこそ発生するものであり、関係が悪ければ退職を検討すること自体がないでしょう。
近年特に増加しているのは、雇用契約最終のイベントとも言える退職時における会社と労働者の対立や違いに関する事例です。なぜこのような退職時のトラブルが増加しているのでしょうか。
当然ですが、その要因は多岐にわたり、一概に言い切ることは難しいです。しかし、詳しく分析してみると、退職時に問題が生じる要因が幾つか浮かび上がってきます。こうした事情が、退職に際してのトラブルの背後にある要因であるようです。
労働市場の変動や経済の波及、そして職場環境の多様化などが影響していることは否定できません。特に労働者側が自己のキャリアと働き方に関してより高い意識を持ち、会社に対する期待が変わってきたことも大きな要因です。
このような複雑な背景を持つ現代労働市場において、円満な退職がますます重要となっています。適切な就業規則の整備は、このようなトラブルの未然防止に向けての一歩と言えるでしょう。労使双方にとって有益な退職プロセスを確立し、労働トラブルを最小限に抑えるためにも、是非専門家のアドバイスを活用してください。
1.解雇に関するトラブル
退職に関わるトラブルの中でも、特に頻繁に発生するのは解雇に関する問題です。この問題が浮上する背景には、就業規則が不十分な点が挙げられます。就業規則の欠点は、具体的な解雇事由や要件が十分に整備されていないことです。以前の記述で述べた通り、多くの企業が市販のテンプレートを採用し、自社の状況に合わせたカスタマイズが不足しています。このため、実際に解雇を検討する際に、要件を満たすかどうかを判断するのが難しい状況が生じます。
私がアドバイスした中規模の石油化学工場の事例がそれを象徴しています。この工場で喫煙違反を繰り返す社員に対して解雇を行う際、喫煙違反は退職事由としては明記されておらず、そのために社員の解雇要件が適合するか否かが曖昧でした。結果的に、解雇の際には労働審判を経て和解金と会社都合退職が合意され、問題の解決には長い期間がかかりました。
こうした事例から明らかなように、就業規則の整備が不十分だと、解雇に関する問題が複雑化し、解決までの時間がかかります。労働トラブルは企業にとって深刻なリスクですが、キチンと整備された就業規則があれば、問題解決が円滑に進む可能性が高まります。私の経験から言えるのは、問題が発生する前に適切な就業規則を整備することが、労使双方の利益にとって不可欠だということです。あなたの会社のために、適切な就業規則を整備し、労働トラブルの未然防止に向けて努力しましょう。
2.退職日に関するトラブル
退職に関連するトラブルの中でも、予想外に多いのが「退職日」に関する問題です。
多くの会社が就業規則において、「退職を希望する日の1カ月以上前に申し出るように」と退職日の規定を設けています。しかしこの規定が引き起こす問題の一つが、退職申し出と業務引き継ぎの調整に起因するトラブルです。
単純なマニュアル作業であれば、トラブルが発生することは少ないかもしれませんが、専門的な部門を持つ一般企業や人数の少ない中小企業などでは、部門ごとの業務や進捗状況が個人に密着していることがあります。
こうしたケースでは、引き継ぎには十分な期間が必要であることが考えられます。従って、会社の業種や規模、従業員数に応じて、就業規則にて「退職の申し出は60日以内に」といった具体的な期限を設けることが検討されるでしょう。
ただし、民法では退職の予告期間を2週間と規定しています。従って、この点は就業規則において補足的に定める必要がある規定であり、会社の事情に合わせて適切な方針を取ることが大切です。退職の手続きは会社と労働者双方の利益を考慮しながら進めるべきであり、適切な規定の設定がトラブルを回避するための一助となるでしょう。
有休消化は認めるべきか?
しかし、状況は複雑で、退職する社員の後任が未定であり、新たな採用が必要な場面では、引継ぎが即座に行われるわけではないこともあります。私の経験から見ても、労使関係が比較的健全であり、常識を持った社員であるならば、引継ぎの適切な期間と有給休暇の考慮を通じて、就業規則の定めにかかわらず、退職の意向を早めに伝えるケースが多いようです。
ただし、問題は、社員と会社の関係が悪化している場合や、高い質を持たない社員である場合などです。このような状況では、引継ぎ期間や有給休暇についての配慮は行われず、実際、私の経験において、特定のマーケティングマネージャーのケースでは、法定の1か月前の退職申し出があったにもかかわらず、その後3日で有給休暇を利用し始めるという事態が発生しました。
こうしたケースでは適切な引継ぎも行われず、有給休暇のみが申請される場合があります。しかしこのような場合でも、有給休暇申請を拒否することはできません。少なくとも労働基準法で規定された日数分(労働基準法第39条)の有給休暇は、法的に保障された権利です。したがって、退職時に有給休暇の消化を認めないことは違法行為となります。
こうした理由から、退職日に関する就業規則の規定は極めて重要です。適切な引継ぎと有給休暇の管理を確保するために、余裕を持った退職日の設定が必要です。それにより、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。
3.就業規則の整備が重要
要するに、退職に関するトラブルは想像以上に頻発しており、その未然防止や軽減のために、就業規則の見直しは不可欠です。
まず、就業規則には一般的に認められる解雇事由だけでなく、貴社の実情に合わせた解雇事由が適切に明記されているか確認が必要です。また、自己都合退職に関するルール(申し出の期限など)が明確に規定されているかも確認が求められます。
しかしながら、これらの要件を満たす会社固有の就業規則を整備することは容易ではありません。時間と労力が必要であり、更に改訂後の規則が法令やその他の規定に適合しているかを検証することは複雑な作業です。これには専門的な知識が必要です。だからこそ、私たちのような社労士に相談することをお勧めします。
私たちの事務所は、これまで多くのトラブル事例を経験してきました。就業規則にまつわる問題を解決するための実務経験と専門知識を有しており、貴社に適した規則を提案し、トラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。私たちと協力して、適切な就業環境を構築し、円満な退職プロセスを確保しましょう。お気軽にご相談ください。